この記事の対象者
結論
介護士は医療行為はできません
一部の行為は許可が出ており実施可能
国は曖昧な書き方が多い、会社にしっかり確認する事
厚労省からの引用文
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること ※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの 注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。
注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。
上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。
出典
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
決まっている事はしっかり守る必要がある
資格がないのに医療行為をするのは犯罪です。
罰金や懲役刑となります。
1番最後にも記述があるように、応急手当てをしてはダメと言ってるわけではないですから、突然の怪我に対してガーゼを当てる事などは問題ないです。
しかし、これを定期的に行い、症状の改善を目指すのは医療行為ですから絶対ダメです。
医療職がやっていいと言ってもダメ
たまに医療職の方々からやっていいですよ、とお許しが出る事があります。
しかし、それは介護士のできる範囲があいまいな書き方の為、お墨付きをくれているのですね。
ただ、残念ながら指示があっても治療に当たる行為はNGなんです。
誰が何といってもダメなものはダメです。
そしてその判断をするのは個人ではなく会社(組織)です。
会社の規定や上司の判断を仰ぎ 勝手な行為をしない事
他社や利用者さんからお願いされて、自分で判断できない場合。
とりあえずやっておこう、この考えは絶対ダメです。
しっかり自身の会社や上司に確認しましょう。
もし勝手に行った行為が医療行為で、それによってそれを受けた方の症状が悪化したら?、もう会社も守れない状態となってしまいます。
ご自身が訴えられてしまう事態とならないよう、しっかり確認しましょう。
最後に
医療行為は絶対に行ってはいけません。
どこまでが医療行為で、どこから介護士がやっていい行為なのか、会社にしっかり確認を取りましょう。
介護士の勝手な判断で行ってはいけません。
同業者や利用者、医療職がOKといったから大丈夫ではないです。
ご自身の会社で行ってよい行為かしっかり確認する事。
まとめ
結論
介護士は医療行為はできません
一部の行為は許可が出ており実施可能
国は曖昧な書き方が多い、会社にしっかり確認する事



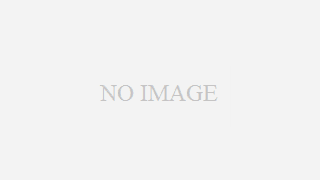
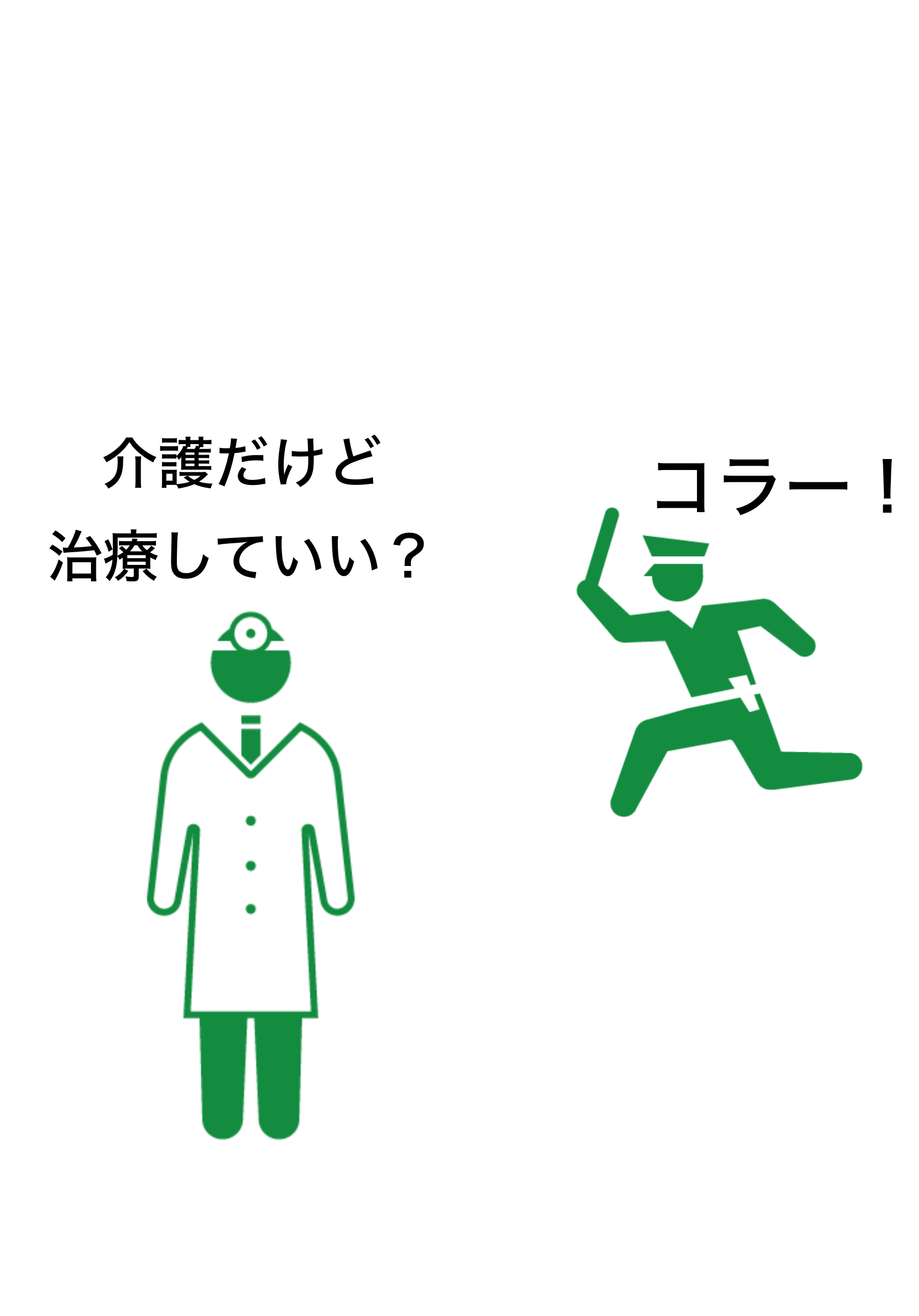


コメント